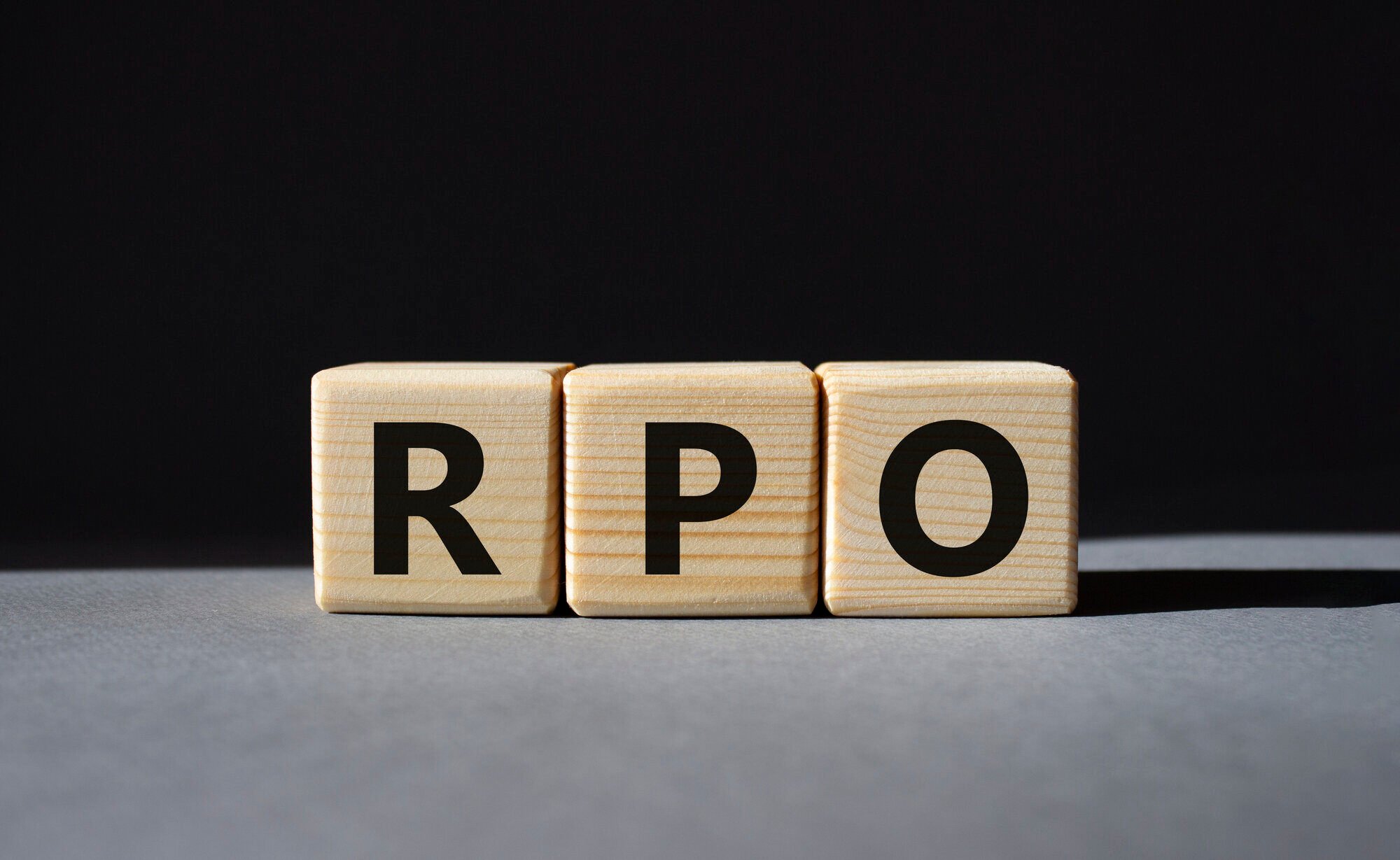エンジニア採用代行(RPO)とは?メリット・デメリットから成功事例を徹底解説【2025年最新】
人手不足や採用難易度の高まりを背景に、企業の採用活動にエンジニア採用代行(RPO)を導入する動きが活発になっています。特にITエンジニア領域では人材獲得競争が激化しており、自社のリソースだけでは必要な人材を確保できないケースが増えています。採用代行を導入することで採用にかかる工数を削減でき、コア業務に集中できるなど様々なメリットがありますが、「採用代行(RPO)は違法ではないのか?」と疑問に思われる方もいるでしょう。
本記事では、エンジニア採用代行の基礎知識やメリット・デメリット、特に中小企業がエンジニア採用代行を導入すべき理由を解説するとともに、採用代行を適切に活用するために知っておきたい許可基準や、利用申請の手順、代行事業者に依頼する際のポイントなど、さらには実際の成功事例までを詳しく紹介します。
目次
- エンジニア採用代行(RPO)とは?
- エンジニア採用代行(RPO)の必要性が高まる理由
- エンジニア採用代行(RPO)の将来性
- エンジニア採用代行(RPO)に依頼できる業務
- エンジニア採用代行(RPO)のメリット・デメリット
- 中小企業がエンジニア採用で採用代行(RPO)を導入すべき理由
- エンジニア採用代行(RPO)を活用し、成功した事例
- 採用代行(RPO)を依頼する流れ
- 採用代行(RPO)に違法性はあるのか?
- 採用代行(RPO)の「委託募集」の許可基準
- 採用代行(RPO)における委託募集時の申請手順
- 採用代行(RPO)事業者に依頼する際のポイント
エンジニア採用代行(RPO)とは?
RPOは"Recruitment Process Outsourcing"の略称で、日本語では「採用代行」と呼ばれます。特にエンジニア採用代行は、ITエンジニア領域に精通した採用のプロに採用業務をアウトソーシングできるサービスのことです。
採用戦略の方針策定や求人媒体・採用要件の決定、スカウトメールの送信、面接日時の調整、選考、採用、内定者へのフォローなど幅広い業務領域を担当します。不特定多数の企業と求職者をマッチングする「人材紹介」に比べ、より企業に近い目線で採用に関与する点が特徴です。
採用代行でできること
採用代行を導入することで、採用にかかわる事務的な仕事を代行してもらえるため、自社で行うべき業務の工数が削減可能となります。具体的には、求人広告の作成や書類の確認、スカウトメールの作成・送信、応募者への対応、面接日程の調整といったルーティーン的な業務を採用代行によって代行できます。
また、採用代行事業者は採用活動を専門に行っているため専門知識を有しています。そのため、その知識にもとづいたコア業務の補助をすることも可能です。たとえば、採用計画の立案や人材要件の定義、内定者フォローといった業務が挙げられます。自社の採用担当者の工数を削減し、他の業務に集中できるようになるほか、プロの視点から採用戦略の立案や採用手法の選定を行い、ミスマッチの減少など効果的な採用を実現できるようになります。
エンジニア採用代行(RPO)の必要性が高まる理由
近年、注目が集まる採用代行ですが、その背景には人事業務の増加・複雑化とエンジニア採用の難易度の上昇があります。
終身雇用制度が揺らぎ転職が当たり前になった現在、転職市場は活性化しており、さらに人口減少・少子高齢化による人手不足の影響もあり採用環境は厳しさを増しています。
こうした中で優秀な人材を獲得するためには、確かな採用ノウハウをもとに求職者へ適切なアプローチをかけなければなりません。しかし、採用活動を自社だけで進めようとすると、採用担当者の業務量は膨大となり、採用のコア業務にリソースを割けず、満足な採用ができないという問題が生じることがよくあります。
また、AIをはじめとした先端技術の発展や、「2025年の崖」に対処するためのDX需要増大もあり、エンジニアの採用は特に難しくなっています。ITに限らず様々な業界でエンジニアの需要が増えている一方、人材の供給が追いついていない状況です。経済産業省の調査によれば、IT需要の伸びが「高位」の場合、2030年には約79万人ものIT人材が不足すると予測されています。
IoTやAI技術の進展、DXの推進など、エンジニアが活躍する領域は近年ますます広がっており、多くの業界でエンジニアの採用需要が高まっています。一方で、エンジニアの母数自体は少なく、スキルや経験の豊富なエンジニアとなるとさらに希少性が高いため、採用競争が激しく自社内のノウハウやリソースのみではなかなか人材採用ができない状況となっています。
このように、近年は企業が求める知識や技術のレベルが高まり、そして経験を持ったエンジニアの争奪戦が激しくなっている状況であるため、採用業務をより強化するべく採用代行が注目されているのです。そこで、IT領域の採用の知見を持つプロの力を借りる採用代行(RPO)の重要性が高まっているのです。
エンジニア採用代行(RPO)の将来性
採用代行は現在注目されているものの、将来性はどうなのでしょうか。
先述のように、人口減少・少子高齢化による人手不足を背景に、あらゆる業界で人材確保が経営課題となっています。さらに、近年は採用方法が多様化しており、その分、採用業務に必要となる工数も増えているため、小規模事業者を中心に自社のリソースだけでは間に合わない企業も少なくありません。こうしたことから、今後も採用代行のニーズは高まると予想されています。
| 年度 | 市場規模 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2021年度 | 628億円 | 15.0%増 |
| 2022年度(予測) | 706億円 | 12.4%増 |
民間の市場調査機関によると、2021年度の採用代行市場(主要3市場計)は前年度比15.0%増の628億円であり、2022年度には706億円に達すると予測され、今後もさらなる市場の拡大が期待されています。
エンジニア採用代行(RPO)に依頼できる業務
エンジニア採用代行(RPO)に依頼できる業務としては、主に以下の6つがあります。
| 依頼可能な業務 | 内容 |
|---|---|
| 1. 採用計画の策定 | 自社が求める人材のターゲット像や採用人数、採用コストなどの計画を策定します。 |
| 2. 採用要件の作成 | 求める人材像をより詳しく設定し、必要となる職務経験やスキルなどの要件を定義したうえで採用要件を作成します。 |
| 3. 採用媒体の選定 | 採用媒体にはダイレクトリクルーティング媒体や求人広告媒体などさまざまな種類・サービスがあり、どれを利用するかによって採用の成否が変わってきます。自社の採用ニーズにマッチした媒体をプロの視点から選定することで採用効率を上げることができます。 |
| 4. スカウトメールの作成 | スカウトメールの文面によって候補者からの反応には大きな差が生まれます。プロのノウハウを借りることで効果的な採用につなげることが可能です。 |
| 5. スクリーニング | 応募者のプロフィールを確認し、自社に適した人材を探し出すスクリーニング業務も代行可能です。 |
| 6. 応募者の対応 | 応募があった候補者との面接日程の調整や、内定後のフォローといった対応も代行してもらうことができます。 |
ITエンジニアの採用を成功させるカギは、転職活動を本格的に始めていない人材にいち早くアプローチをかけ、自社に合った人材を獲得することです。
そのためには、多種多様な採用媒体から最も適切なものを選定したり、昨今活用されているダイレクトリクルーティングやスカウトメールを活用したりするなどの専門的なノウハウが必要になります。プロに協力してもらうことで、採用にかけられる社内のリソースを最適化しながら効率的に優秀な人材を獲得しやすくなります。
エンジニア採用代行(RPO)のメリット・デメリット
以下では採用代行の理解を深めるために、採用代行のメリット・デメリットをそれぞれご紹介します。
採用代行の5つのメリット
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 1. 採用のコア業務に集中できる | 手間のかかるルーティーン的な業務を任せることができるため、自社の採用担当者は採用計画・戦略の立案や合否判定などのコア業務に集中できます。これにより求める人材をより適切に見極められ、内定者フォローもきめ細かく行えるなど、採用力の強化を図れます。 |
| 2. 自社で採用専任者を採用するよりも比較的安価に導入できる | 採用力強化のために採用専任者を確保する場合は、最低でも社員1人分の人件費がかかります。サービスや提供する企業にもよりますが、採用代行の導入費は月数十万円程度であるため、担当者を新たに採用するよりも安価に抑えられる可能性があります。 |
| 3. 採用活動全体または一部でもアウトソーシングができ、担当者の負担が減る | 採用代行は、最終的な合否判定以外の採用業務全体、またはその一部をアウトソーシングできるため、自社の採用担当者の負担を軽減できます。特に、人的リソースに乏しい中小企業にとっては大きなメリットです。 |
| 4. 求人媒体の機能をフル活用できる | 採用代行を行う企業は採用業務を専門としているため、各求人媒体の機能や傾向を熟知しており、自社に適した媒体の選定や媒体の機能活用などが期待できます。 |
| 5. 採用活動の質を向上させるためのノウハウを習得できる | 採用代行では、これまでの実績や経験にもとづき、採用に関する助言を受けたり、進捗状況の共有を通じて改善点を洗い出したりしてくれるため、専門家の持つノウハウを学べるメリットもあります。情報共有を密に行うなどコミュニケーションを図り、PDCAを回すことでより採用活動の質を高めることができます。 |
採用代行の3つのデメリット
一方で、採用代行には以下のデメリットもあり、利用する際には以下の点について注意が必要です。
| デメリット | 詳細 |
|---|---|
| 1. 依頼しただけでは採用ノウハウを蓄積しにくい | 先述のように採用代行事業者と密なコミュニケーションをとることでノウハウを習得できるメリットがありますが、単に依頼しただけでは自社の社員が採用の実務経験を積めないため、ノウハウがなかなか蓄積されません。 採用状況の確認や細かな現状分析、改善点の洗い出しなどの情報共有も積極的に行う必要があります。 |
| 2. コミュニケーションを図らないと齟齬が生じる | 採用代行事業者に採用業務を丸投げしてしまうと、自社が求める人材が集まらないなど、ミスマッチが生じる可能性が高まります。1つ目のデメリットと同様、定期的かつ密なコミュニケーションを取ることが重要です。 |
| 3. 1つの施策だけでなく複数の施策を用意する必要がある | エンジニア採用は難化していることもあり、たとえば求人媒体のみのアプローチでは求める人材をなかなか確保できないこともよくあります。そのため、リファラル採用やダイレクトリクルーティングなど、複数の施策をあらかじめ候補として用意する手間がかかる点もデメリットです。 |
中小企業がエンジニア採用で採用代行(RPO)を導入すべき理由
以上のようにさまざまなメリットのある採用代行ですが、中小企業などは特に採用代行を導入すべきです。
一般に、中小企業やスタートアップ、ベンチャーなど人員に限りのある企業は、収益に関わる部署に優先的に人員が配置される傾向があります。そのため、採用担当者が通常業務と採用業務を兼務していることが多く、人員や時間、予算といったリソースを採用業務に十分にあてられないケースも少なくありません。
また、専任の採用担当者がいたとしても専門家ではないことも多々あります。エンジニア採用ともなると、採用に関する知見に加え、エンジニア・IT業界特有の知識やスキル、経験の有無を判定するための知見が必要とされます。こうした課題を自社だけで解決し、エンジニア採用を成功させることは現実的には困難です。
そのため、採用代行(RPO)事業者と協力し、効率的な採用活動を進めることが必要となります。
エンジニア採用代行(RPO)を活用し、成功した事例
成功事例①:企業規模20名|6ヶ月で7名のエンジニア採用に成功
企業規模20名のあるIT企業では、企業規模が小さいために採用担当者が他の業務と兼務している状態となっており、採用業務にリソースを割けない課題がありました。そこでエンジニア採用代行(RPO)を導入し、採用計画の策定から改善、ダイレクトリクルーティング運用等の業務支援を依頼したところ、採用担当者の業務工数が削減されただけでなく、運用6ヶ月で7名のエンジニア採用に成功しました。
【支援内容】
| 支援項目 | 詳細 |
|---|---|
| 採用計画の策定 | 企業のニーズや市場状況に基づいた実現可能な採用計画を策定 |
| 採用オペレーション改善 | ヒアリング・改善・面接用フロー共有 |
| ダイレクトリクルーティング運用 | 2媒体での運用、緊急休日対応含む 書類選考・スクリーニングスカウト・応募者コミュニケーション・内定者コミュニケーション |
| 求人広告運用 | エン転職・doda運用(求人原稿・募集要項作成)・エージェントコントロール |
成功事例②:企業規模370名|4ヶ月で6名のエンジニア採用に成功
企業規模370名のあるIT企業では、中途でのエンジニア採用の成果をなかなか得られず、採用業務の改善が課題となっていました。そこでエンジニア採用代行(RPO)を導入し、現状の採用オペレーションについてのヒアリングや改善を図ったうえで、ダイレクトリクルーティングでの書類選考やスクリーニングスカウトの支援を受けた結果、運用4ヶ月で6名のエンジニア採用に成功しました。
【支援内容】
| 支援項目 | 詳細 |
|---|---|
| 採用計画の策定 | 獲得人数の共有・エージェント提案 |
| 採用オペレーション改善 | ヒアリング・改善・カジュアル面接・面接用フロー共有 |
| ダイレクトリクルーティング運用 | 2媒体での運用 書類選考・スクリーニングスカウト・応募者コミュニケーション・内定者コミュニケーション |
| 求人広告運用 | 契約中のtype・doda引継ぎ運用(求人原稿・募集要項作成) |
採用代行(RPO)を依頼する流れ
採用代行への依頼は以下の流れに沿って行います。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP1 相談・ヒアリング |
事前に自社の採用における近年の実績や課題感などを整理しておき、相談・ヒアリングを行います。ヒアリングの中で、より具体的な課題の抽出やおおまかな予算を算定します。 |
| STEP2 見積もり |
ヒアリングの内容をもとに、目標達成のためのロードマップなどサービス内容の詳細を明示し、価格の確認・承諾などを行います。 |
| STEP3 契約・設定 |
秘密保持契約の締結を行い、契約します。契約に際しては、法務部門等と相談し内容について精査する必要があります。 |
| STEP4 サービス開始 |
契約が締結された後は、採用代行事業者側で担当者の割り当てや体制整備を行い、打ち合わせの内容に沿って実際にサービスを開始します。 |
採用代行(RPO)に違法性はあるのか?
採用担当者の中には、「採用代行(RPO)は違法である」という情報を見聞きしたことのある方もいるかもしれません。そこで、ここからは実際に採用代行(RPO)に違法性があるかを見ていきます。
許可が取れていれば違法ではない
結論から言えば、基本的に採用代行(RPO)のサービス自体は違法ではありません。選考や合否の決定を自社で行い、採用試験の作成をはじめとする事務的な作業や、求職者のスカウトを採用代行(RPO)事業者に委託する場合は違法ではなく、また厚生労働省や都道府県労働局長への届け出も不要です。
ただし、次節でご紹介する許可が必要なケースで届け出をしていなかったり、利用開始時の手続きに不備があったりする場合などは違法となる場合もあるため注意が必要です。
採用代行(RPO)の利用が違法になるケース
採用代行(RPO)が違法になるケースとしては以下の場合が挙げられます。
| 違法となるケース | 説明 |
|---|---|
| 1. 許可申請の欠如 | 採用代行(RPO)サービスの内容が「委託募集」に該当しているにもかかわらず、事業者(受託企業)と委託企業が許可申請をしていなかった場合 |
| 2. 虚偽申請 | 許可申請に虚偽の内容があった場合 |
| 3. 許可前の募集開始 | 申請が許可される前に募集を開始した場合 |
| 4. 個人情報の不適切管理 | 求職者の個人情報を適切に管理しなかった場合 |
| 5. 労働関係法違反 | 業務内容が労働関係法を違反している場合 |
上記のいずれかに該当し、職業安定法違反と見なされた場合は、罰せられる可能性があります。根拠の条文は以下の通りです。
「許可を受けずに法第36条第1項の委託募集を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰に処せられる(法第64条第6号)」
法的許可が必要な「委託募集」とは?
採用代行(RPO)事業者への委託内容が「委託募集」に該当する場合は、企業と採用代行(RPO)事業者がともに厚生労働省か都道府県労働局長から許可を得る必要があります。
委託募集とは、労働者の募集や選考自体を自社の従業員ではない第三者に委託することです。委託募集を行う際でも、職業安定法で規定されている基準を満たし、届出をしていれば違法にはなりません。
採用代行(RPO)の「委託募集」の許可基準
委託募集の許可基準については「職業安定法第36条」に記載されています。細かい条件はあるものの、コンプライアンスに配慮した経営を行っていれば条件は満たせます。
厚生労働省の資料によると、委託側・受託側それぞれの委託募集の許可基準は以下の通りです。
採用代行における委託側(企業)の許可基準
| 許可基準項目 | 内容 |
|---|---|
| 労働条件 | 労働条件が適正であり、かつ明示されている |
| 賃金水準 | 同地域、同業種の賃金水準と比べて著しく低い金額ではない |
| 社会保険加入 | 労働・社会保険に適切に加入している |
| 募集期間・報酬 | 募集期間が1年未満であり、受託業者に支払う報酬は、支払われた賃金額の100分の50未満までである(委託募集に必要となる経費が特に高額になる特段の事情がある場合を除く) |
採用代行における受託側(代行事業者)の許可基準
| 許可基準項目 | 内容 |
|---|---|
| 法的資格 | 青年被後見人または被保佐人でない |
| 専門知識 | 労働関係法令および募集内容・職種に関して十分な知識を有している |
委託側・受託側ともに委託労働環境や雇用条件に問題がないかという点が主な基準です。また受託側としては、採用に必要な判断能力を有しているかが重要になります。
採用代行(RPO)における委託募集時の申請手順
採用代行(RPO)における委託募集では、以下の手順を踏んで申請します。
| 申請手順 | 内容 |
|---|---|
| ① 必要な申請書類を用意する | まずは申請に必ず必要な厚生労働省発行の「委託募集許可等申請書(様式第3号)」を用意します。必要事項を記入し、提出準備を進めましょう。 また、申請書を提出する際は、申請書の内容を証明できる帳簿などの関係書類も必要になります。そのため、関係書類の準備もあわせて行いましょう。 |
| ② 期限までに書類を提出する | 書類の準備が完了したら、定められた期限までに提出を行います。 提出先は募集人数によって異なり、もしも1つの都道府県で30人以上の募集をかける場合、もしくは全体での募集人数が100名以上になる場合は、厚生労働大臣の許可が必要です。その他の場合は管轄の都道府県労働局長の許可が必要です。 都道府県労働局長の許可を得る場合は、募集開始月の14日前までに、厚生労働大臣の許可を得る場合は開始月の21日前までに上記の書類を提出します。 |
| ③ 審査結果を待つ | 申請後には審査結果を待ちます。審査結果は、許可・不許可・条件付き許可のうちいずれかが通知されます。 なお、委託許可申請については、受託側が代わりに行うことが可能です。申請の工数を削減したい場合は、許可申請を代行してくれる採用代行(RPO)事業者へ任せると良いでしょう。 |
採用代行(RPO)事業者に依頼する際のポイント
採用代行(RPO)事業者に依頼する際には、以下の4点を押さえておくことが重要です。
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 1. 依頼業務を明確にする | 採用活動は繁雑な業務が多く、場合によっては許可申請が必要です。そのため、依頼したい業務を明確にしておかないと、どの業務を業者に任せるべきか分からなくなり、採用代行(RPO)を有効活用できない可能性があります。 |
| 2. サービスの提供許可を取得しているかを確認する | サービス内容に「委託募集」を含む場合、許可基準を満たしているか、正当に事業を実施しているかを確認する必要があります。 |
| 3. 過去に同業界の採用実績があるかを確認する | 過去の採用実績も依頼するうえで重要な判断材料になります。どの業界・職種に精通しているかを確認しておくことが大切です。 |
| 4. 委託したい業務内容に対応可能かを確認する | 事務作業などの部分的な委託業務を行う事業者もあれば、採用戦略の策定から施策の実行まで全体のサポートが可能な事業者もあります。採用代行(RPO)事業者のサポート範囲を確認し、自社の予算を踏まえて対応してもらいたい業務を洗い出し、最適な事業者を選定することが重要です。 |
「アイティ人事」の採用代行サービス
「アイティ人事」は、企業の採用活動を効率化するための採用代行(RPO)サービスを提供しています。貴社の課題に合わせた柔軟なサポートで、無駄なコストを抑えながら優秀な人材を確保できます。
まとめ
エンジニア採用代行(RPO)は、採用活動に関する業務を外部委託するサービスであり、企業の採用担当者の負担軽減や採用力の向上を図ることができます。特に人的リソースの限られた中小企業にとっては、エンジニア採用などの専門性の高い人材確保において大きなメリットがあります。
本記事では、エンジニア採用代行の概要や必要性、依頼できる業務内容、メリット・デメリット、成功事例から法的な側面まで詳しく解説しました。基準を満たし、しかるべき許可を取っていれば採用代行は違法ではないこともお分かりいただけたでしょう。
本記事の内容を把握したうえで、採用代行サービスを上手に活用して、効率的な採用活動を実現しましょう。エンジニア採用でお悩みの方は、ぜひ採用代行の導入をご検討ください。